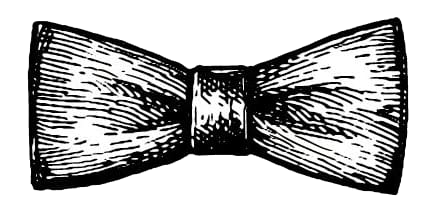その一瞬のために

遠い親戚に、目の見えないおじさんがいた。
数回しか会わないままわたしは大人になり、彼はもう死んでしまったけれど、もう三十年以上も前のこと、法事で半日を一緒に過ごしたことがあった。彼は温和で物腰が柔らかく、退屈している子どもたちに「何でも好きなものを持っておいで、僕は目は見えないけれどそれが何なのか当ててみせるから」と遊んでくれた。子どもたちは競うように、部屋にあった湯呑やペンや紙切れや自分のおもちゃや母親たちのバッグの中の細々したものまでを手当りしだいに持っていき、一瞬の迷いもなく正解を言ってみせる叔父さんに歓声をあげた。それは楽しいひとときだったけれど、わたしはそれからしばらくのあいだ、そのおじさんのことが頭から離れなくなった。それはおじさん自身のことというよりも、おじさんの見ているものについてだった。
母によると、彼は後天的に病を得て失明したらしい。目が見えないということは光のない世界にいることなのかと訊くと、そういうことやな、と母は言った。ただ、おじさんは今はもう目が見えないけれど、見えていた時期がある。つまりおじさんは、光がどういうものかを知っているし、光の記憶を持っているのだ。おじさんにもう一度会うことがあれば、訊いてみたいことがあった。それは、頭の中で思いだす光と、実際に見る光はいったいどれくらい違うのか、あるいは、どれくらい似ているのか、ということ。結局それを訊く機会はなかったけれど、それからというもの、わたしは夜眠るまえ、瞼を閉じあとに広がる暗闇の中で、昼間の光を思いだす、というのを繰り返すようになった。記憶のなかの光というものが現在の暗闇の中で、どんなふうにどれくらい光るものなのか、どうしても知りたかったのだ。
時は流れて、わたしは小説家になり『夏物語』という小説を書いた。生殖倫理をベースに、フェミニズムや貧困、反出生主義や階級問題について書かれた物語であると紹介されることの多いこの小説は、三世代の女性たちの関係と語りが軸になっている。主人公の夏子とわたし自身に共通点はあるけれど(たとえば大阪の貧困家庭で育ったことや、小説を書いていることなど)、しかし当然のことながら、それ以外の要素はやはりフィクションだ。けれどもひとつだけ、わたしの体験と感情をそのまま使って書いた部分があって、それは、自分を育ててくれた祖母にたいする、夏子の思いのすべてだ。
祖母は2019年の初夏に亡くなった。祖母はわたしを母親のように育て、色々なことから守ってくれた。わたしはいつか祖母が死んでしまうことが恐ろしくて、必ずやってきてわたしを捉えるだろうその時を想像しては泣いているような子どもだった。祖母は優しく、その存在は、わたしが子ども時代を生きることのできた、ほとんど唯一の理由そのものだった。
物心ついた頃から恐れていた祖母の死が現実のことになって一年半が経つけれど、今も体の芯が定まらないような、どこかふらふらとした気持ちで過ごしている。写真を見れば、涙が出る。祖母は老衰で亡くなった。生活は苦労ばかりだったが、大病もしないまま年を重ねて97歳になり、結果的にこれ以上はないくらいの大往生になったと思う。世の中にはある日突然引き裂かれるように大切な人と離別させられて、とつぜん襲いかかった理不尽に必死に耐えながら、なんとか生きている人たちがいる。それなのに、こんなに長いあいだ一緒にいられて最期を見届けられたわたしなどが、まだめそめそと泣いていることを思うと、自分には悲しむ資格などないように思えてしまう。実際、なぜ今もまだこんなに悲しいのかが自分でもわからない。おかしな言い方になるが、大人のわたしではなく、祖母の死を心から恐れていた子ども時代のわたしが、今もまだわたしのどこかに残っていて、その部分が、わたしの感情を使って悲しみつづけているような、そんな感覚なのだ。
わたしは子どもの頃から祖母と顔も体型もよく似ていて、着替えをするときなどにふと自分の下半身を見下ろすと、反射的に祖母の体を思いだすほどだった。延命措置のための点滴をわたしの判断で外し、最後の夜は病室でふたりきりで過ごした。生きる力が少しずつ祖母の体から失われていくのを見つめながら、わたしは祖母の額や、点滴で変色してしまった腕や太ももを、何時間もさすり続けた。あんなことがあった、こんなこともあった、ありがとうねと話しかけながらさわる祖母の体は温かくて、まだ血が通っていて、この数日のうちに、いま目の前にいる祖母が体ごと焼かれて灰になって消えてしまうのだと思うと、どうしていいのかわからなかった。意識のある祖母と最後に話したのは、その2週間前のことだった。ふたりで笑って写真を撮って、またすぐに来るからねと言って手を振って、病室のドアを閉めたあのときが、最後になったのだなと思った。終わりは、いつだって終わりの顔をしてわたしたちを訪ねるようなことはしない。すべてが過ぎ去ってから、あれが最後だったと気づくだけだ。そんなことはわかっているのに、もしかしたら、あれ以外の「最後」を作ることができたのではないかと思ってしまう。もしあの翌日にもう一度祖母を見舞っていたら。様子を見にきていたら。これからあと何回、こんなふうに振り返ってから知る「最後」を経験することになるのだろう。
祖母の体を何時間もさすりながら、意識のない祖母に話しかけながら、いまさわっているこの祖母の肌を忘れないでいようとずっと思っていた。こうして撫でて、さすっていることを忘れないでいようと思っていた。今見えているぜんぶを可能な限り、覚えていようと強く思った。でも同時に、どうすれば今、こうして手のひらで感じているこの感覚を覚えていられるのだろうとも考えていた。感覚を覚えておくというのは、どういうことなのだろう。祖母をさすりながら、だんだんわからなくなっていった。いつも一緒にお風呂に入っていた祖母の体。たくさん血豆があって、子どもの頃、それが破れたらそこからたくさん血が出て祖母が死んでしまうじゃないかと不安になって、全部に絆創膏を貼ってとお願いしたら、にこにこ笑って心配せんでええよと笑った祖母。いなくなっていく人を、失われてゆく感覚を覚えておくというのは、本当のところ、いったいどうすることなのだろうか。
気がつくと、祖母の腕や脚を、夜中も朝も昼もずっとさすっていたあの数時間のことを考えている。あの時、祖母の肌は温かくて、まだそこで生きていて、わたしは確かに祖母にさわっていた。でももう、今は祖母はいなくなって、二度と祖母の肌にふれることはできなくなってしまった。わたしは、そのことについて考える。そして遠い昔の子どもの頃に、暗闇の中の光について想像していたことを思いだす。目の見えなくなったおじさんが、頭の中で思いだしていたかもしれない光のことを考える。それは、光を見ていることとは違うのだろうか。もうさわることはできない祖母の肌の感触を思いだすことは、祖母にふれているということとは、やはり違うことなのだろうか。
誰かにさわれることと、もうさわれないこと。誰かが生きていることと、死んでもういないこと。現実に会うことと、夢や思い出の中で会うこと。目のまえの光と、記憶の中の光──本当のところ、これらはいったい何が違うのだろう。本当に、死んだ人には二度とさわることができず、失われた光は二度と戻ってこないのだろうか。あるいは、わたしたちには行けないだけで、それらがじつは、みなおなじであるというような、そんな世界がどこかにあるのだろうか。わからない。でも、そんな世界が存在しなくても、辿り着くことができなくても、それらが本当はみなおなじであると心からそう思える瞬間を、一瞬だけでも成立させるために、わたしは物語を書いているのだと思う。